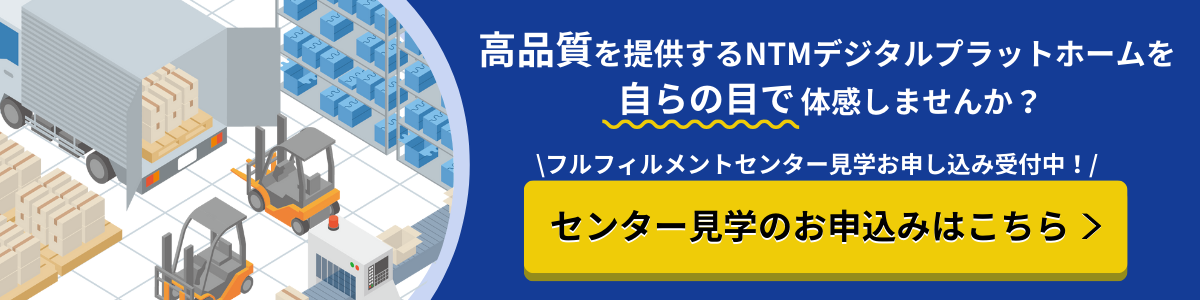食品物流の特徴を徹底解説!物流の流れや業者の選び方とは

食品物流とは、どのような物流をさすのでしょうか。今回は、食品物流について、いくつかの分類に分けつつ、それぞれに求められる品質管理や特徴を解説します。
また、食品物流における課題や対策についてもご紹介します。
目次
- 食品物流について
- 常温食品
- 冷蔵・冷凍食品
- 食品物流の特徴・課題
- 【要素別】食品物流の課題と対策
- 徹底した温度管理
- 賞味期限・消費期限管理
- 衛生管理・防犯管理
- コスト管理
- 配送品質
- 食品物流の最新トレンド
- 食品物流未来推進会議
- コールドチェーン
- システム導入によるJIT配送の実現
- 食品物流の自動化(AI予測技術・IoTスマートパッケージング技術)
- 食品物流の流れ
- 食品物流を効率化する方法
- 作業のマニュアル化
-
倉庫管理システムの導入
- DX化
- 物流業務を委託する
- 食品物流の委託先を選ぶ基準
- 自社製品を管理できる環境であること
- 倉庫管理のサービスについて
- 食品物流の委託例
- 食品物流は商品管理を任せられる業者に委託を
食品物流について

食品物流とは、人が口にするものの物流をさす言葉です。他の物流とは品質管理の基準が異なり、特殊な設備や基準が設けられています。食品物流は、主に「常温食品」と「冷蔵・冷凍食品」の2つに分けられます。
常温食品
常温食品とは、常温で保管しても品質に問題がない商品です。例えば、缶詰や調味料、お菓子などが当てはまります。
常温食品は消費期限が長く、管理がしやすいといえます。ただし、常温食品の中にも、チョコレートやグミなど、一定の温度よりも高くなると溶けたりくっついたりするものがあります。品質を損なわないよう、商品に合った適切な温度での運搬が大切です。
冷蔵・冷凍食品
冷蔵・冷凍食品は、名前の通り温度調整が必要な食品です。
冷蔵食品として、青果や魚・肉などがあげられます。適切な温度で輸送しなければ、鮮度が保たれません。
冷凍食品とは、アイスクリームや冷凍食品です。冷凍食品は、温度の上昇により解凍されると品質が落ちます。そのため、適切な温度管理のもとで輸送する必要があります。
食品物流の特徴・課題

食品物流の特徴として、「食品に合った適切な温度管理を徹底すれば食品の品質を保てる」という点があげられます。そのため、食品物流の主な課題は温度管理にかかわるものです。
また、食品には賞味期限や消費期限があります。温度管理だけでなく日付管理も必要不可欠であり、倉庫や加工現場には厳しい管理環境が求められています。
食品を適切に保存・管理するためには専用の倉庫が必要です。しかし、温度管理や環境を整えると手間や費用がかかります。これが原因で事業の拡大に踏み出せない企業も存在します。
>>ECビジネスにおける物流の重要性とは?特徴と課題について解説!
【要素別】食品物流の課題と対策

ここからは、食品物流における課題と対策を要素別に解説します。それぞれの課題に対して、どのようにすれば解決できるかを把握しておきましょう。
徹底した温度管理
食品物流には徹底した温度管理が欠かせません。食品に合った温度管理が求められるため、企業は複数種類の倉庫や冷蔵庫を用意する必要があります。
食品の鮮度を一定に保つためにも、条件の合う倉庫を用意したり、コールドチェーンを活用したりする対策をしましょう。取り扱っている商品や最適温度に合わせて対応することで、商品の品質を保てます。
賞味期限・消費期限管理
食品を安心して口に入れてもらうために、賞味期限・消費期限の確認は徹底しましょう。もし賞味期限の切れた食品が店頭に並べば、企業の信頼低下の原因となります。
しかし、取り扱っている商品数が多い企業や人手不足の企業の場合、期限のチェックには時間や手間がかかるでしょう。
そのようなときは、業務のデジタル化を推進して、期限の管理を円滑に行えるような工夫をします。手作業の業務が少なくなれば、ミスが減り、作業効率が上がります。
また、業務の一部を外部に委託することで、社員の負担を減らす方法もあります。
衛生管理・防犯管理
食品を保管している倉庫は、異物の混入を防ぐためにも徹底した衛生管理が必要です。
害獣やその他の生きものが侵入できないように対策しましょう。例えば、作業入り口でのエアシャワー設置や手洗いルールの厳守が対策としてあげられます。
また、外から関係者以外の人が入って来ないように、防犯管理もしっかり行いましょう。意図的な異物混入や窃盗などを未然に防げます。
コスト管理
コスト管理とは、取り扱っている仕入れの数や在庫数、納品数などの管理です。
食品は、売上や人気の動向を踏まえた管理が必要です。おろそかにすると、消費期限が切れたり傷んでしまったりします。傷んでしまった食品は廃棄処分となります。
廃棄を避けるためにも、過去の売上や毎年の傾向から販売数を予測して、できるだけロスを出さないような生産や発注を心がけましょう。食品によっては時期やイベントによって需要が生まれます。世間のイベントや流行のチェックも欠かさず行ってください。
配送品質
食品物流において、品質を管理する場面は保管のときだけではありません。配送中も、保管している倉庫と同じ環境を保つ必要があります。
具体的な温度管理としては、以下があげられます。
・15℃程度:チョコレート菓子やワイン
・-18℃以下 冷凍食品
食品に合った温度で配送しないと、食品が傷んだり、解凍が原因で劣化する恐れがあります。配送品質を保った状態で、消費者の元に食品を届けましょう。
>>当社のフルフィルメントサービス(スゴロジ)の紹介はこちら
食品物流の最新トレンド

ここからは、食品物流に関するトレンドや、話題になっている2024年問題と食品物流の関係性、食品物流の自動化やシステム化について解説します。
>>最新の物流体制を体感!当社物流センター見学の詳細はこちら
食品物流未来推進会議
食品物流未来推進会議(SBM)とは、「物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン」をもとに、物流に関する自主行動計画を定めて物流の適正化および生産性向上を目指すものです。
物流の適正化・生産性向上のほか、荷待ち時間や荷役作業の削減などについても取り決めが行われています。
定められた計画については、今後の進捗状況によって適正化および生産性向上を目指し、見直しを測る予定だとされています。
労働環境悪化によるドライバー不足
食品物流の業界では、労働環境の悪化によってドライバーが不足しています。
食品物流業界では、納品先での長時間待機があったり、運転以外の作業が多かったりと、ドライバーにかかる負担が大きいことが課題です。
また、非合理的な慣習が撤廃されていないことも問題視されています。
2027年には需要に対してドライバーが27%不足するようになるといわれており、ドライバー不足の解決及び労働環境の改善が求められています。
2024年問題は食品物流にも影響
運送ドライバーに大きな影響を及ぼす2024年問題は、食品業界にも影響を与えます。
2024年問題とは、2024年4月以降に、働き方改革関連法案の一環で運送ドライバーの時間外労働に上限がつくことで起こる問題です。この法案により、年間960時間までしか業務が追加できなくなります。
これにより、これまで時間外労働で稼いでいた運送ドライバーの給与が低下して、離職率の増加が予測されています。
運送ドライバーの数が減ると、食品物流にも影響が出るでしょう。食品物流に関する企業は、業務の効率化や自動化を図り、自社の物流に影響が出ないような工夫をすることが求められます。
物流は環境負荷が大きい業界
食品物流を含め、物流業界は地球温暖化の原因であるCO2排出や梱包資材による環境負荷が多い産業だといえます。
今後の地球環境および社会の持続可能性を考えて、物流活動による環境課題への対応が求められています。
環境対策を求める声が強まっていることは、人手不足や労働環境などの課題と共に、物流業界にとって大きな負担だといえるでしょう。
企業や団体によっては、グリーン物流を推進したり、モーダルシフトを行ったりして環境問題対策を行っているところもあります。
コールドチェーン
コールドチェーンとは、生産から消費までの過程で、低温管理が必要な食品を適切な温度に保ちながら、途切れることなく商品を届ける仕組みです。低い温度下での管理を連続して行うことからコールドチェーンと名付けられました。
コールドチェーンは、食品の鮮度を保ったままユーザーへ食品を届けられる方法として注目されています。コールドチェーンにより、生鮮食品の保存期間が長くなり、広い地域に対しての流通が可能になりました。また、食品だけでなく医薬品の品質も保てます。
コールドチェーンの大きなメリットは、食品の廃棄ロスが減ることです。一方、デメリットとして、温度管理の徹底により費用がかかることがあげられます。
システム導入によるJIT配送の実現
ジャストインタイム物流とは、必要なものを必要なときに配送する物流の仕組みです。
これを実現できれば、在庫を最小限に抑えられます。ただし、在庫切れのリスクがあり、その都度配送する配送費用もかかるため、デメリットも踏まえたうえで取り組まなければなりません。
これらのデメリットは、共同配送を取り入れると解消されます。
食品物流の自動化(AI予測技術・IoTスマートパッケージング技術)
業務の効率化を図るために、システムの自動化が進められています。自動化の例として、膨大な量のデータを収集・分析できるAI予測技術を使った情報収集があげられます。
また、loTスマートパッケージング技術も注目されている技術の1つです。これを導入すると、センサーやデバイスにより運送中の食品の温度や湿度、在庫管理・製品の品質保持などをリアルタイムで監視できます。
食品物流の流れ

食品物流の流れについて、解説します。
まず、食品の原料生産者から食品メーカーへ原料が送られます。食品メーカーが自社農園を持っている場合もあるでしょう。
つぎに、食品メーカーで原料を調理・加工し販売する商品のかたちにします。その食品は、メーカー倉庫で保管され、品質が維持されます。
その後、倉庫から問屋へ商品がわたり卸売店へと届けられます。ここまで、商品が消費者の目に留まることはほとんどありません。最後に、小売店から消費者の元へと商品が届きます。
食品物流を効率化する方法
食品物流の課題の多くは、人手不足や非効率的な作業によるものです。
このような課題を解決するためには、いくつかの手段があります。
ここからは、食品物流を効率化するための方法について紹介します。
>>EC物流を成功させるためのポイントを解説!つまずきやすい注意点も!
>>物流業務効率化のメリットとは?課題解決に向けた方法や事例
作業のマニュアル化
作業の効率化に効果的な方法の1つが、作業のマニュアル化です。
マニュアル化することで、作業内容が均一化され、一定の品質が保てます。
また、先輩が教えなくてもマニュアル通りにやれば作業内容を習得できるため、新人教育が楽になる点もメリットだといえるでしょう。
作業の流れが決められていないと、担当者が退職したとき、新人に作業内容が伝わらなくなる恐れもあります。
作業の内容をマニュアル化しておけば、作業内容について伝達できなくなる可能性が大きく減少します。
倉庫管理システムの導入
作業を効率化したいときは、システムを導入することも重要です。
倉庫への入荷から出荷までに発生する作業を、一括で管理できるシステムを導入すれば、作業内容の確認が容易になります。
作業を一元管理していない場合、時間のかかる作業があったり、ミスの確認が難しかったりなどの問題が生じます。
リアルタイムで作業内容を確認できるシステムを導入すれば、担当者以外でも作業内容についての確認が可能です。
作業の効率化は費用削減にもつながるため、積極的に導入しましょう。
DX化
物流のDX化(デジタル技術を用いた業務内容の改善)によって、業務の効率化や労働環境の改善を実現できる場合があります。
DX化には初期費用がかかるものの、長期的な目線で見ればランニングコストを減らしたり業務にかかる時間を削減したりできます。
物流の現場におけるDX化として、考えられる方法は、以下の通りです。
・ドローンの導入
・マニュアルの電子化
・自動運転トラックの導入
・仕分けやピッキングの自動化
・在庫管理システムの導入
物流業務を委託する
自社だけでは費用の削減や作業の効率化が難しい場合は、外部に作業を委託することも1つの方法です。
物流に関する専門的なノウハウを持つ企業に業務を委託すると、業務の効率化と費用・作業時間の削減が実現します。
食品物流を得意とする企業に委託することで、自社で行う場合よりも物流品質を向上させることも期待できるでしょう。
近年、国土交通省も専門的な会社への委託の導入を推進しており、多くの企業が注目しています。
食品物流の委託先を選ぶ基準
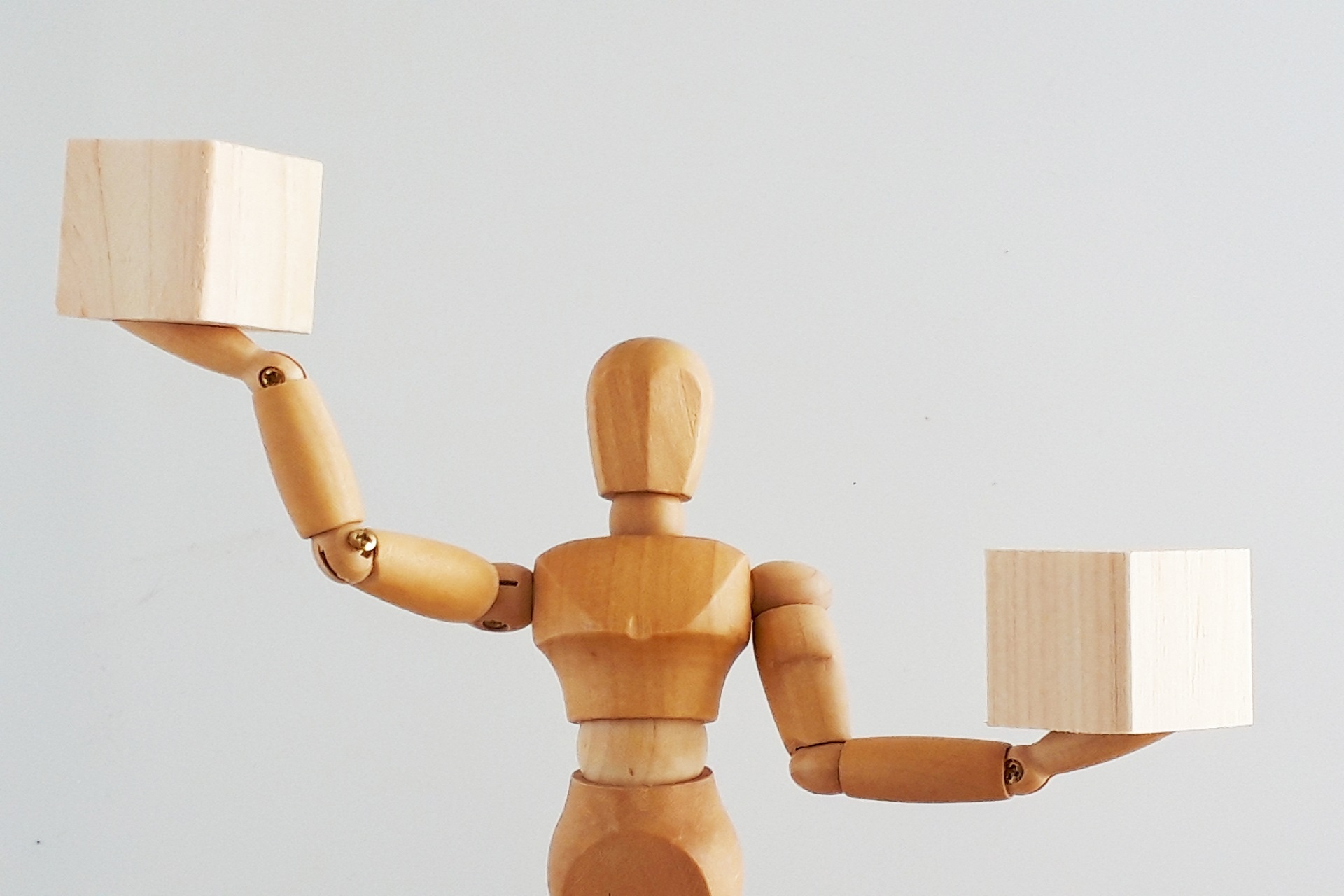
食品物流の業務において、外注や委託を考えている企業もあるでしょう。委託先を選ぶ基準はいったいどのようなものでしょうか。ここからは、委託先を選ぶ基準を2つ紹介します。
>>物流業務の委託サービスを利用するメリットは?サービスの種類や導入の流れ
自社製品を管理できる環境であること
最初に、自社で取り扱っている食品を管理できる環境が整っていることを確認しましょう。
商品によって適切な温度管理や環境は異なります。委託先の倉庫に自社製品を保管して、品質が保たれるかどうかは非常に重要です。
また、自社製品の生産数に合う規模の倉庫が存在することも確認します。食品の大きさや生産数をもとに、「どの程度の規模の倉庫を希望するか」をはっきりさせます。
倉庫管理のサービスについて
「倉庫管理」に含まれるサービスやシステムは、企業によって異なります。どこまでのサービスが含まれているかは、委託先を選ぶ際の重要なポイントです。
倉庫管理には、以下のようなサービスがあります。
・在庫管理システム
・配送準備
・品質チェック、賞味期限切れチェック
・梱包作業
例えば、梱包が必要な食品を扱っている場合、その商品に合った梱包方法を行える委託先がおすすめです。また、トラックドライバーが足りない企業は、小売店や消費者への配送までも請け負ってくれるような業者を選びましょう。
食品物流の委託例

記事の最後に、食品物流の委託例を紹介します。
とある外食チェーンの大手企業は、既存システムのまま入庫〜出荷の倉庫管理業務委託できる業者を探していました。取扱品は多岐にわたり、常温・冷蔵・冷凍とそれぞれの対応が求められます。
委託先の物流倉庫では、専用チームを発足し、クライアントの希望通りに、そのままのシステムで全ての業務を委託できるような対応をしました。
>>物流業務の委託サービスを利用するメリットは?サービスの種類や導入の流れ
食品物流は商品管理を任せられる業者に委託を

今回の記事は、食品物流の要素や、物流に関する課題と対策を解説しました。食品の品質を保ったまま消費者の元へ届けるには、専門分野に特化した業者への委託がおすすめです。自社商品の種類や特徴に合う業者へ委託しましょう。物流業務の一部をアウトソーシングすることで、社内の負担が減り、業務の効率化や売上の向上が見込まれます。
>>当社のフルフィルメントサービス(スゴロジ)の紹介はこちら

.png)