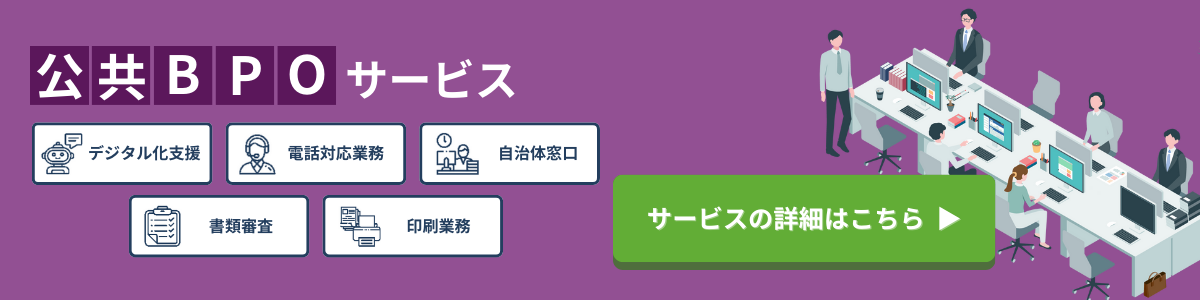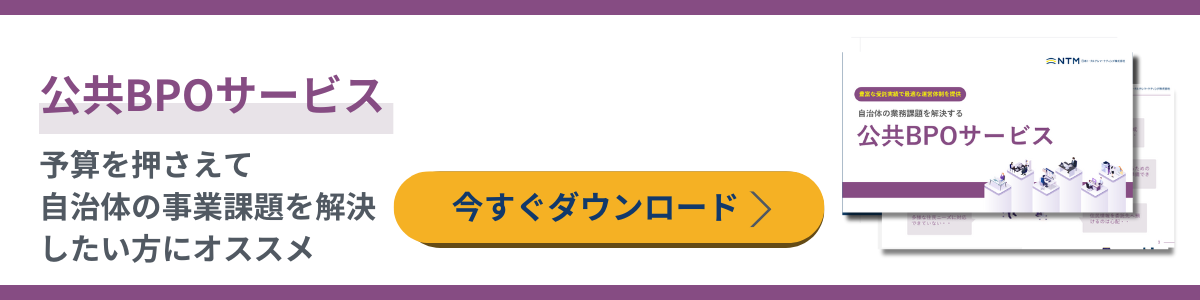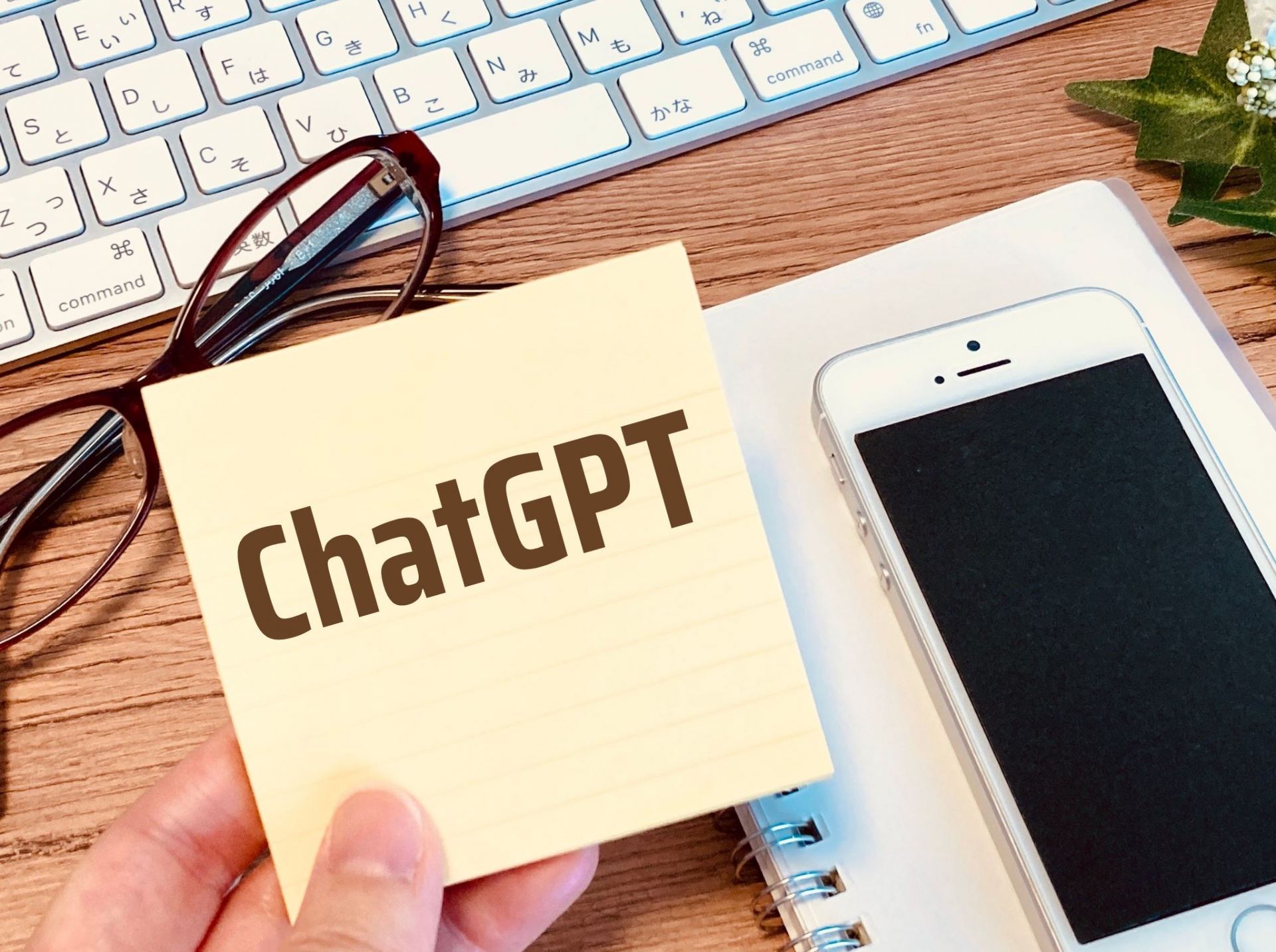日本のスマートシティへの取り組み|自治体事例や注目される理由、効果も紹介

最新技術を取り入れた都市「スマートシティ」。
私たちの暮らしがより豊かに、快適になるように多くの地方自治体ではスマートシティに向けた取り組みを進めています。
この記事では、自治体でどのように取り組んでいるのか、スマートシティが注目される理由やその進め方について解説します。
目次
- スマートシティとは
- スマートシティが注目される理由
- スマートシティに期待される効果
- 交通の効率化
- 環境エネルギー問題の解決
- 生活の利便性向上
- 最新!スマートシティに取り組む自治体一覧
- 北海道札幌市
- 福島県会津若松市
- 東京都渋谷区
- 東京都港区
- 神奈川県横浜市
- 埼玉県さいたま市
- 長野県伊那市
- 富山県富山市
- 兵庫県加古川市
- 香川県高松市
- 福岡県北九州市
- 千葉県柏市
-
スマートシティの進め方
- STEP 1 初動
- STEP 2 準備・共有
- STEP 3 計画・戦略策定
- STEP 4 実証・実装
- スマートシティに関するQ&A
-
スマートシティに活用される科学技術は?
- スマートシティのメリットは?
- スマートシティにはデメリットがある?
- スマートシティを成功させるポイントは?
- まとめ:公共BPOサービスは当社にお任せください
スマートシティとは

スマートシティとは、最先端の技術を用いて、都市のさまざまな情報を収集・分析することで、企業や消費者の活動を快適で便利にすることを目指す都市です。
都市内に張り巡らされたセンサーやカメラ、スマートフォンなどから情報が集められ、さらにその情報をAIが分析し活用しています。
似ている言葉に「スーパーシティ」がありますが、「スマートシティ」は最先端技術を用いた都市の利便性の向上を意味しますが、「スーパーシティ」は課題解決の手段の1つとして最先端技術を活用し、未来都市を実現することを意味します。
スマートシティが注目される理由

さまざまな地方自治体でスマートシティに向けた取り組みが進められていますが、なぜ今スマートシティが注目されているのでしょうか。現在日本では、少子高齢化やそれに伴う労働人口の減少などの課題があります。それらの課題は、最先端技術を用いることで解決できる可能性があるため、さまざまな地方自治体でスマートシティの取り組みが進められています。
さらには、近年関心が高まっている地球環境やSDGsの観点から、最先端技術を使うことでエネルギーの効率化・最適化に取り組めることも、スマートシティへの注目が高まっている理由のひとつです。
スマートシティに期待される効果

スマートシティは、都市の抱える課題を解決し、持続可能な社会を実現できます。交通の効率化や環境負荷の軽減、そして生活の利便性向上など、さまざまな改善が期待されます。
以下では、スマートシティでどのような効果が期待できるのかを詳しくまとめました。
交通の効率化
スマートシティは、都市部の移動をスムーズにし、より快適な暮らしを実現できます。
交通の効率化では、交通データをリアルタイムで収集して分析し、先進的な技術を活用した交通管理が可能です。その結果、渋滞の緩和や移動効率の向上が期待できます。
例えば、公共交通機関の利用促進を目指すMaaS(Mobility as a Service)も、スマートシティを目指すうえで効果的です。この取り組みでは、交通手段を最適に組み合わせて予約や決済を一括で行えるため、都市全体の移動効率向上が期待できます。
交通の効率化を実現するスマートシティは、地域全体の効率化や活性化が期待できます。
環境エネルギー問題の解決
スマートシティは、環境エネルギー問題を解決し、持続可能な都市づくりを推進します。
例えば、再生可能エネルギーの導入や資源循環型システムで、ゴミの削減が期待できます。
具体的には、太陽光や風力などの再生可能エネルギーを利用し、ゴミ処理システムの導入で資源を最大限活用できる仕組みです。その結果、温室効果ガスも削減でき、エネルギー効率のよい都市づくりが可能です。
環境エネルギー問題に対応するスマートシティは、地球環境保全とクリーンな都市づくりを実現できます。
生活の利便性向上
スマートシティは、市民の生活を便利で快適にします。
行政サービスのデジタル化やオンライン手続きの普及で、従来かかっていた手間や時間が大幅に削減されます。オンライン診療では医療アクセスが容易になり、市民の健康を促進できるでしょう。
また、スマートシティでは、住民はスマートフォンを使って行政手続きや医療サービスを簡単に利用できます。さらに、リアルタイムデータを活用した移動計画では、通勤や買い物の待ち時間が減少するため、日常生活における利便性が格段に向上します。
このように、市民の生活を快適にするスマートシティは、ストレスの少ない暮らしを提供できる画期的な取り組みといえるでしょう。
最新!スマートシティに取り組む自治体一覧

市民生活の利便性の向上に寄与する「スマートシティ」。
今やさまざまな自治体によって特色ある取り組みが進められています。
ここからはスマートシティに取り組んでいる地方自治体について、その取り組み内容を具体例とともに取りあげます。
北海道札幌市
札幌市では令和5年から、少子高齢化やそれに伴う経済的な影響、積雪や災害への対策といった札幌市の抱える課題に対して、最先端技術活用の推進に取り組んでいます。
2024年度は「札幌市スマートシティ推進協議会」が運営する「新・さっぽろモデル事業」がタブレットやスマートフォンを通して、地域住民の健康増進やコミュニティの活性化に役立つサービスの提供を始めました。
より地域のニーズに沿ったサービス提供ができるように、サービス企画案の募集なども行っています。
出典:札幌市「札幌市スマートシティ推進協議会」
福島県会津若松市
人口減少や少子高齢化の課題を抱える福島県の会津若松市では、決済や教育、ヘルスケアなど、さまざまな分野でのICTの活用推進をビジョンとして掲げています。
2024年9月には、スマートシティ会津若松のサービスを体験するイベント「AiCTまつり」が開催されました。
同イベントでは、会津若松の便利なサービスの体験やプログラミングのデジタル体験に加えて、デジタルに関する相談会も行われました。
出典:会津若松市「スマートシティ会津若松」について」
東京都渋谷区
東京都の渋谷区では、さまざまな年代・性別・人種などの多様性をエネルギーに変えることを目標に、スマートシティの推進に取り組んでいます。
渋谷区の特徴的な取り組みとしては、さまざまなデータをグラフで視覚化した「シブヤシティダッシュボード」です。渋谷区に関するデータを視覚化し、スマートシティの取り組みに参加する各機関との連携に役立てています。
出典:渋谷区「渋谷区スマートシティ推進基本方針 」
東京都港区
東京都港区では、防災対策や回遊性の向上を目指してスマートシティの推進に取り組んでいます。
具体的には、独自データを収集・活用した3D都市モデル「バーチャル竹芝」です。交通・防災などさまざまな分野のサービス提供によって地域の問題解決を目指しています。
港区の実行計画によると、2024年度には高潮が発生した際の混雑シミュレーションとして、地区内訓練での実装や、都市の開発シミュレーションなどを実施します。
出典:港区「Smart City Takeshiba 実行計画(東京都港区)」
神奈川県横浜市
神奈川県横浜市は、地球温暖化や地球環境などの課題解決のために、2010年の早い段階からスマートシティの推進に取り組んでいる都市です。
これまで培ったノウハウを活かし、令和元年からは社会情勢の変化も踏まえたうえで、脱炭素化に向けたスマートシティの実現を目指すマスタープランを定めています。
2024年10月には「アジア・スマートシティ会議」を開催し、世界への発信活動にも取り組んでいます。
出典:横浜市「横浜スマートビジネス協議会(YSBA)」
埼玉県さいたま市
埼玉県さいたま市では、「スマート・ターミナル・シティさいたま実行計画」として、
モビリティサービスの充実、ライフサポート型MaaSの構築、スマートプランニングによるウォーカブルな都市空間・環境の形成を掲げています。
注目は、新たな交通システムの展開によって、移動のしやすさ向上や自家用車への依存といった課題の解決に取り組んでいる点です。
他にも、アプリでの情報発信や都市基盤の整備などを進め、市民の利便性向上や地球環境のために取り組んでいます。
出典:さいたま市「スマートシティさいたまモデルの推進」
長野県伊那市
高齢化の進む長野県伊那市では、交通の不便さや第一次産業の後継者不足などの課題を抱えていました。
そこで、AIを搭載した自動配車乗り合いタクシーのサービスや、ドローンの活用による物流サービスの展開に取り組みました。
ドローンを活用した買い物サービス「ゆうあいマーケット」では、高齢者が普段慣れ親しんでいるケーブルテレビのリモコンから操作でき、地域の実態に即したサービスを展開しています。
出典:伊那市「日本を支えるモデル都市の構築を目指して – 伊那市」
富山県富山市
富山県富山市では、これまで取り組んできたコンパクトなまちづくりをさらに深めるため、デジタル技術を用いたスマートシティへの取り組みを推進してきました。
富山市は地域の課題を解決するためのプラットフォーム「SCRUM-T」を運営しており、企業・団体・地方自治体などさまざまな機関が登録しています。
富山市センサーネットワーク事業では、富山市のセンサーネットワークを業務に活用したり、企業に提供したりすることで産業の活性化につなげているものもあります。
出典:富山市「スマートシティとやま – 富山市」
兵庫県加古川市
兵庫県加古川市では、安心・安全なまちづくりのためにデジタル技術を導入しています。
学校や小学校通学路付近約1500か所の「見守りカメラ」を導入したことによって犯罪件数は減少しました。現在では悲鳴や車の接近をAIが検知しお知らせしてくれる「高度化見守りカメラ」も設置し、更なる犯罪や事故の未然防止に取り組んでいます。
また、小さなタグを持つことで「見守りカメラ」に検知され、スマートフォンで行動を確認できる「見守りサービス」も導入しています。
出典:加古川市「暮らしをより良く!スマートシティ加古川」
香川県高松市
香川県高松市では、複数の分野のデータを収集・分析するプラットフォームを構築しています。
市民全員がデジタル技術を活用でき、どこからでも利便性を享受できる「スマートシティたかまつ」の実現を目指す高松市では、ICT機器を用いた教育活動の推進や、高齢者の見守りシステムの導入なども進めています。
出典:高松市「スマートシティたかまつ – 高松市」
福岡県北九州市
福岡県北九州市では、工業都市としてエネルギーに着目したスマートコミュニティ創造事業を進めています。
ICT基盤を整備し、エネルギーに関するデータを見える化するなど、脱炭素化・省エネルギー化に向けたサービス提供や仕組みづくりです。
また、観光産業についてもデジタル技術を取り入れており、混雑状況センシングやAR・VR展示、ダイバーシティに向けた取り組みも進めています。
出典:総務省「福岡県北九州市におけるICTの技術仕様の検証のための地域実証」
千葉県柏市
千葉県柏市の「柏の葉スマートシティ」は、公・民・学が連携して進める最先端のスマートシティプロジェクトです。
この取り組みでは、AIやIoTなどの最新技術を使って自動運転や健康支援など多分野で実証を進行中です。
住民の声を取り入れながら、生活の質の向上と持続可能な都市モデルの実現を目指しています。
出典:
・千葉県柏市|「柏の葉スマートシティ」
・国土交通省|柏の葉スマートシティ 実行計画フォローアップ 2020資料」
スマートシティの進め方

「スマートシティを導入したいけど進め方が分からない」と悩む人は、少なくありません。
スマートシティをスムーズに進めるためには、以下の順序で行うことがおすすめです。
- 初動
- 準備・共有
- 計画・戦略策定
- 実証・実装
それぞれ詳しく解説します。
STEP 1 初動
スマートシティを成功させるポイントは、取り組みの発意と推進体制の構築です。
初動段階では、取り組みの方向性を定めるための基盤づくりが欠かせません。スムーズにプロジェクトを進めるためには、関係者間で連携体制を構築し、地域ごとの課題を明確にする必要があります。
具体的には、自治体や企業がリーダーシップをとり、スマートシティにおける取り組みを提案します。そして、住民や専門家を巻き込んで推進体制を構築し、地域一丸で課題を洗い出しましょう。
初動段階に、スマートシティの方向性や推進体制を明確に策定すれば、プロジェクト全体の成功につながります。
STEP 2 準備・共有
スマートシティを進める際は、住民のニーズを理解し、目的や目標を関係者間で共有することが不可欠です。
スマートシティの効果を最大限高めるためには、住民の意見やニーズを聞き入れてそれらを反映する必要があります。また、関係者間での目的の共有も大切です。
これらを踏まえ、スマートシティをスムーズに進めるためには、アンケート調査やワークショップを通じて住民のニーズを把握するとよいでしょう。その後、交通利便性の向上や環境負荷への低減など、具体的な目標を策定します。そして、情報を関係者間で共有し、一体感をもって取り組むことが重要です。
住民のニーズを分析し、明確な目標を関係者間で密に共有することが、スマートシティの価値を最大化する鍵となるでしょう。
STEP 3 計画・戦略策定
スマートシティを効率的に進めるためには、具体的な計画と目標達成に向けた詳細な戦略が重要です。
実現可能な計画と戦略をもつことで、プロジェクトの進捗を測定しやすくなり、円滑なリソース配分が実現できます。具体的には、プロジェクトの目標に基づき、以下の項目を決めるとよいでしょう。
- 目標
- 課題
- KPI
- 収集データの決定
- 各データの取り扱い方法
- 資金計画
- 全体スケジュール
また、技術や協力企業の選定もこの段階で行いましょう。
計画段階での綿密な準備が、スマートシティの効果的な実現につながります。
STEP 4 実証・実装
スマートシティの成功には、実証・実装を実施し、サービスの効果を分析しつつアップデートを重ねることが不可欠です。
スマートシティは進化する取り組みであり、実装後の検証と改善を通じて、プロジェクトの完成度を高める必要があります。また、市民の理解を得たうえで取り組むことが不可欠です。
分かりやすい事例をあげると、買い物へ行くことが難しい高齢者を対象とした、ドローンを使った買い物サービスです。このプロジェクトでは、需要の高いエリアを選定し、お試しキャンペーンで住民に「使ってもらう期間」を設定しました。その後、分析や実証、改善を繰り返し、利便性の高さを受けて導入エリアを拡大しています。
このように、実証と改善をし続けるプロセスが、スマートシティの持続的な成功には欠かせないことが分かります。
スマートシティに関するQ&A

ここまで、スマートシティについて、取り組んでいる地方自治体やその具体的な取り組み、注目される理由などについて説明してきました。
さまざまな自治体で取り組まれているスマートシティには、どのような最先端の科学技術が活用されているのでしょうか。
ここでは、スマートシティに関するよくある質問をいくつか紹介します。
スマートシティに活用される科学技術は?
スマートシティに活用される科学技術のうち、代表的なものには「IoT」「ICT」「AI」などがあります。
「IoT」とは、車や家電などにセンサーを取り付け、遠隔操作を可能にする技術です。
情報通信技術である「ICT」は、情報収集や処理に活用され、人間の学習能力を模倣する人工知能である「AI」はデータの分析に活用されます。
そしてこれらの技術が連携するための「データ連携基盤」の技術も活用されています。
スマートシティのメリットは?
スマートシティの大きなメリットは、人手不足や高齢化に対応できる点です。
実態に即したサービスを展開することで高齢者のケアにもつながります。
また、災害時や感染症対策として、ロボットやAIの活用も進められています。
AIの活用で交通整理もできるため、高齢化による労働人口の減少が見られる中で、これらの課題に対応できることはスマートシティの大きなメリットといえるでしょう。
スマートシティにはデメリットがある?
スマートシティは利便性の向上に寄与するものではありますが、いくつかのリスクや課題もあります。
1つは、プライバシーやセキュリティ面のリスクです。スマートシティでさまざまなサービスを提供する際に膨大なデータを活用するため、そのプライバシーやセキュリティの保護が重要です。
また、時間や費用の問題もあります。効果を実感するためには長期的な運用となり、時間や費用がかかる場合もあるため、地域住民からの理解を得ることが大切です。
スマートシティを成功させるポイントは?
スマートシティの推進を成功させるポイントは3つあります。
それは「市民の参加を促す」「市民の意見を聞く」「市の特徴を活かす」です。
スマートシティの推進には市民の関心や積極的な参加が重要です。
市民の方々に参加してもらい、困っていることやどのようにすればこの街がよくなるのか、感じている課題や提案を聞くことで地域の実態に即したサービスに取り組めます。
また、市の特徴を活かすことで長期的なスマートシティの推進にもつながります。
まとめ:公共BPOサービスは当社にお任せください
ここまで、スマートシティについて詳しく解説してきました。
少子高齢化や環境問題など、複雑化する社会課題を抱える日本において、最先端技術を用いたまちづくりは大きな意義があります。
日本トータルテレマーケティングでは、公共BPOサービスを通じて自治体業務の効率化や住民サービスの向上を支援しています。窓口業務やコールセンター運営、申請処理からシステム構築まで幅広く対応可能です。こうした取り組みは、スマートシティの実現に向けた基盤づくりにもつながります。